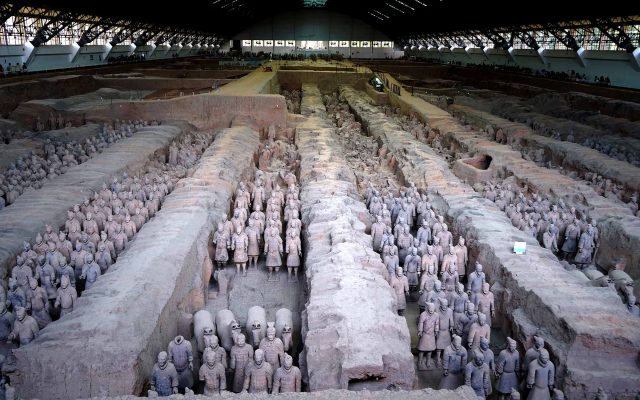中国取材レポ① ようやく中国!今こそ中国!準備万端で便利に楽しく旅しよう
2ページ目
現地での通信環境を確保しよう

通信環境が整わないときに紙のガイドブックが手元にあると心強いのは言うまでもありません。ですが、オンラインサービスをすべて切り捨てて中国を旅するのは現実的ではありません。携帯端末で通信環境を確保する方法を準備しておきましょう。
いちばん安上がりなのは、ホテルや公共施設、飲食店等のフリーWi-Fiを利用する方法。まあまあどこででもつなぐことはできます。ただし中国特有の事情によって、Google、Yahoo!など海外由来のサービスや、みなさんがいつもお使いのX、Instagram、Facebook、LINEといったSNSは使えません。
金楯と称される電子の壁で中国国内や外部との通信が管理されているからで、それでもいつものサービスを使いたいなぁという方は、この壁を越える手段を考えなければなりません。旅行者にとって一般的な方法は、ざっくり4つあります。
1.レンタルWi-Fiを使う
あらかじめネットで申し込んで空港等で受け取るレンタルWi-Fiに、セキュリティ強化のためにVPN(バーチャル・プライベート・ネットワーク)のオプションを付けます。各国で積み上げてきた実績がありますので、こういうふうに使いたいという要望に応えられる機器を用意してくれます。Wi-Fiルーターの充電を忘れないようにすれば、心強い味方になります。
2.日本のキャリアが提供する海外ローミングを利用する
docomo、au、Softbank、Rakuten Mobileなどのキャリアでは、1日単位の海外プランを提供しています。海外ローミングは金楯の頭越しに通信しますので、いつものSNSなども金楯の影響を受けずに使えます。あんまりお金に頓着しないのなら、お手軽です。
3.中国国内で使えるSIMカードを使う
物理的なカードをお手持ちの携帯端末のカードスロットに挿して使います(画像左)。スロットが2つある機種なら、今使っているSIMカードはそのままで、空いているスロットに挿せばOKです。1つしかない機種は、今のSIMカードを抜いて挿し替えます。
注意する点は「香港で売られている、中国大陸で使えるカード」を入手することです。香港製のSIMは今なお上述の金楯を飛び越えて世界中のネットにつなぐことができるからです。amazonや楽天など日本国内のウェブストアで難なく購入でき、違法性はありませんのでご安心ください。お値段も、レンタルWi-Fiや海外ローミングよりずいぶん安く、日本で使っているときと同じように端末を扱えます。また、レンタルWi-Fiと違って、携帯本体の電池残量だけを気にすればいいのも楽チンです。
4.中国国内で使えるeSIMを使う
eSIMは、物理的なカードではなく、仮想のSIMを端末に登録して使います。eSIMに対応している携帯端末なら、中国のeSIMを買って登録すれば、いつものキャリアと切り換えて使えるようになります。eSIMに対応していない機種でも、同様の機能を提供するアプリケーションをインストールして使う方法があります。
こちらも注意点とメリット、入手方法は、SIMカードと同じです。
今回はeSIMをiPhoneで利用することに
「利用期間6日/最大5GB」で1900円弱。SNSとメールと多少のネットサービス利用といった使い方なら5GBあれば余ると思いますが、映像系のYouTubeやNetflixを日本にいるときと同じ勢いでガンガン視聴したい人には全然足りません。そういう人はホテルのWi-FiにVPNを挟んでうまくつながることを神仏とご先祖様に祈るか、海外を旅している間くらいは非日常的な日々に楽しみを見出す努力をしましょう。
eSIM購入時には、登録用のデータが記されたメールと、画像の右に写っているようなペラ紙1枚だけが手元に届きます。メールかペラ紙に載っている二次元コードを使いたい携帯端末で読み込むと、自動的にeSIMが登録されます。想像以上に楽々です。万が一登録されないときは、メールに記された登録情報を、端末の「設定>モバイル通信>eSIMを追加」で打ち込めば大丈夫です。こうなると楽々とは言えませんが、困難を極めるほどでもなく、まあ普通です。ここまでを自宅でやっておきます。
往路の飛行機内で、「設定>モバイル通信」にある「SIM」の項で、登録されている中国のeSIMを選択して「オン」にします。続いて「モバイル通信」のいちばん上の「モバイルデータ通信」でオンになったeSIMを選んでおきましょう。これで、空港に着いて電波が届くようになると、いつの間にやら中国の回線につながってくれます。
ちなみに、このeSIMにより外界につながっているiPhoneでテザリング(ほかのタブレットやPCをネットにつなぐこと)もできました。テザリングは便利ですが、消費するデータ通信量がそのぶん増えるので、使用上限に達しないよう注意しましょう。細かい設定をする必要はありませんが、eSIM提供側から設定の仕方を詳しく記したPDFが届きますので、いざというときのためにプリントしておくか、オフラインでも閲覧できる状態で携帯端末に保存しておくと安心です。
電源の確保も重要

通信の準備はできた、となると次に忘れてはならないのは電源の確保です。
いったんホテルを離れるとずっと外にいる旅先では、容赦なくじわじわと(筆者のiPhoneはくたびれているのでみるみるうちに)減っていくバッテリー残量表示が目に入るのは心臓によくありません。必要十分なモバイルバッテリーを常に鞄に忍ばせておくことを強くおすすめします。対応するケーブルの予備も含めて持っておくと安心感が増します。
モバイルバッテリーに用いられるリチウム(リチウムイオン)電池は、落としたときなどの衝撃で傷み、突然発火する事故をたまに起こしているため、各航空会社では持ち込みにあたってふたつの制限を設定しています。
1.国際線、国内線を問わず、バッテリーの入っているすべての機材は預け荷物にできない
うっかりスーツケースに入れたまま預けるとX線検査に確実に引っかかり、呼び出しを受けたり、合鍵で荷物を開けられてバッテリーを没収されたりします。必ず機内持ち込みの荷物に入れておきましょう。
2.モバイルバッテリーの容量によって機内持ち込みにできる数が決まっている
航空会社による細かい違いもありますが、日中国際路線の主力航空会社ではおおむね次のとおりです。
- 100Wh以下:いくつ持ち込んでもヨシ(中国国際航空は50Wh以下8個まで、100Wh以下2個まで)
- 101~160Wh:2個まで
- 161Wh以上:ひとつでも持ち込んだらダメ
容量はバッテリーの裏や横や底に記されていますが「Wh(ワットアワー)」という表示を見つけられないものがあります。モバイルバッテリーの容量表示は従来より「mAh(ミリアンペアアワー)」が一般的だからです。
画像の2点は、筆者が旅先で持ち歩いている大容量モバイルバッテリーです。ほんのりと写っているとおり、下は「12100mAh」。上は「20100mAh」で、親切なことに「72.36Wh」と換算値も併記してあります。つまりこの2つは100Whに満たないので、いくつでも持ち込めるというわけです。
モバイルバッテリーの「Wh」は、「mAh」を1000で割った数値に、3.7V(ボルト)をかけると得られます(上述の例では微妙に計算結果が合っていませんがご容赦ください)。「20000mAh」前後なら全然平気ということが上述からおわかりかと思いますが、お手元の品を念のため確認しておきましょう。
計算上、「27000mAh(≒100Wh)」以下ならいくつでも、これを超えて「43000mAh(≒160Wh)」以下なら2個まで、それ以上は持ち込み不可、ということになります。持ち込むときはショートを起こさないよう絶縁しておくよう推奨されています。ケーブルを抜き、電源があるなら電源を切って、ひとつずつ別の袋に入れておくくらいで大丈夫です。
持ち込み制限ではないけれど大事なこと
そして最後にひとつ大事なことを。
モバイルバッテリーのなかには、画像でご覧いただているような「仕様」がどこにもプリントされていないものがまれに存在します。いやそんなものはないだろうとおっしゃいますか? あるんです! 筆者はコロナ禍前に、映画館で購入した鑑賞記念グッズとしてのモバイルバッテリーを意気揚々と持っていき、到着空港のセキュリティで「Wh」不明を指摘され、まんまと没収されました。「Wh」不明品は没収されると知っていたのですが、自分のお気に入りにプリントされていないとはつゆほども思っていなかったのでした。お気をつけください。そしてお気に入りのモバイルバッテリーは旅に持っていってはいけません。

筆者
地球の歩き方書籍編集部
1979年創刊の国内外ガイドブック『地球の歩き方』の書籍編集チームです。ガイドブック制作の過程で得た旅の最新情報・お役立ち情報をお届けします。
【記載内容について】
「地球の歩き方」ホームページに掲載されている情報は、ご利用の際の状況に適しているか、すべて利用者ご自身の責任で判断していただいたうえでご活用ください。
掲載情報は、できるだけ最新で正確なものを掲載するように努めています。しかし、取材後・掲載後に現地の規則や手続きなど各種情報が変更されることがあります。また解釈に見解の相違が生じることもあります。
本ホームページを利用して生じた損失や不都合などについて、弊社は一切責任を負わないものとします。
※情報修正・更新依頼はこちら
【リンク先の情報について】
「地球の歩き方」ホームページから他のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。
リンク先のコンテンツ情報は弊社が運営管理しているものではありません。
ご利用の際は、すべて利用者ご自身の責任で判断したうえでご活用ください。
弊社では情報の信頼性、その利用によって生じた損失や不都合などについて、一切責任を負わないものとします。